第6問
貨幣需要に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答
群から選べ。
a 貨幣は流動性が高いので、利子率の上昇によって取引動機による貨幣需要は増
加する。
b 現金は物価上昇によって価値が増加するので、利子率の上昇によって資産選択
の動機による貨幣需要は減少する。
c 現金は安全性の高い金融資産であり、利子率の上昇によって資産選択の動機に
よる貨幣需要は減少する。
d 将来の不確実性が高いと見込まれるとき、利子率の上昇は予備的な動機による
貨幣需要を増加させる。
- a:誤 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
正解!
不正解...
正解はa:誤 b:誤 c:正 d:誤です。
問題に戻る
第7問
生産物市場の均衡条件が以下のように表されるとき、減税の乗数効果を大きくす
るものとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
生産物市場の均衡条件 Y= C + I + G
消費関数 C= C0 + c(Y- T)
投資支出 I= I0
政府支出 G= G0
ただし、Y は所得、C は消費支出、C0 は基礎消費、c(0 < c < 1)は限界消費性
向、T は租税、I は投資支出、G は政府支出である。
- 基礎消費の増加
- 投資支出の増加
- 限界消費性向の上昇
- 政府支出の増加
- 限界貯蓄性向の上昇
正解!
不正解...
正解は限界消費性向の上昇です。
減税の乗数効果を大きくする要因について考えると、以下のように分析できます。
減税の乗数効果
減税によって可処分所得が増加し、その結果、消費支出が増えることで総需要が増加します。乗数効果は、この変化がどのように経済全体に波及するかを示す指標です。乗数効果が大きくなる要因は、主に消費支出の変化に関連しています。
各選択肢の分析
○基礎消費の増加
基礎消費が増加すると、初期の消費水準が上がりますが、これは減税の直接的な影響とは言えません。
○限界消費性向の上昇
限界消費性向(c)が上昇すると、所得が増加したときに消費に回る割合が増え、減税の効果が大きくなります。これは乗数効果を大きくする要因です。
○限界貯蓄性向の上昇
限界貯蓄性向が上昇すると、所得の増加に対して消費が減少するため、乗数効果は小さくなります。
○政府支出の増加
政府支出の増加は直接的に総需要を押し上げる要因ですが、これは減税そのものの効果とは別の要因です。
○投資支出の増加
投資支出の増加も総需要を押し上げる要因ですが、減税の効果とは直接的には関係ありません。
結論
したがって、減税の乗数効果を大きくするものとして最も適切な選択肢は『 限界消費性向の上昇』です。限界消費性向が高まることで、所得の増加がより多くの消費支出を生むため、乗数効果が大きくなります。
問題に戻る
第8問
財政の自動安定化装置(ビルトイン・スタビライザ―)としての機能が比較的強い
と想定される税の仕組みとして、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。
a 利潤に対して累進的に課せられる法人所得税
b 全ての人に同額が課せられる定額税
c 生活必需品に対して課せられる消費税
d 一定額までの所得には課税を免除する個人所得税
- bとd
- aとc
- aとb
- bとc
- aとd
正解!
不正解...
正解はaとdです。
財政の自動安定化装置(ビルトイン・スタビライザー)は、景気変動に対して自動的に働き、景気が悪いときに経済を刺激し、景気が良いときに経済を冷やす役割を果たします。これには、税制や社会保障制度が重要な役割を果たします。
以下の選択肢について分析します。
各税制の自動安定化機能
a 利潤に対して累進的に課せられる法人所得税
法人の利益に対して累進的に課税されるため、景気が良いときには法人の利益が増えて税収が増え、景気が悪いときには利益が減って税収も減ります。これにより、景気変動に対する調整が行われやすく、自動安定化装置としての機能が強いといえます。
b 全ての人に同額が課せられる定額税
定額税は景気の変動にかかわらず一定の税負担を課すため、自動的に景気に応じて税収が変動することはありません。自動安定化装置としての機能は弱いです。
c 生活必需品に対して課せられる消費税
消費税は景気に左右されにくく、特に生活必需品に対する消費税は人々の消費行動があまり変わらないため、自動安定化装置としての機能は弱いです。
d 一定額までの所得には課税を免除する個人所得税
所得が一定額を超えた部分に対してのみ課税されるため、所得が低いときには税負担が減り、所得が高いときには税負担が増える仕組みです。これは累進課税の要素を含んでおり、景気変動に対応しやすく、自動安定化機能が強いです。
適切な組み合わせ
aとdはともに累進的な性質を持っており、自動安定化装置として機能が強いです。
したがって、最も適切な組み合わせは aとdです。
問題に戻る
第9問
日本(円)と米国(ドル)を例にして、為替レートの決定を考える。為替レートの決
定に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。
a 輸出の増加によって日本の経常収支の黒字が拡大すると、為替レートには円高
ドル安の圧力が働く。
b 輸出の増加によって日本の経常収支の黒字が拡大すると、為替レートには円安
ドル高の圧力が働く。
c 米国の金融資産の収益率が高くなることで日米の金融資産の収益率の格差が拡
大すると、日本の金融収支は赤字になり、為替レートには円高ドル安の圧力が働
く。
d 米国の金融資産の収益率が高くなることで日米の金融資産の収益率の格差が拡
大すると、日本の金融収支は黒字になり、為替レートには円安ドル高の圧力が働
く。
- aとd
- aとc
- bとc
- bとd
正解!
不正解...
正解はaとdです。
為替レートの決定に関する記述について、それぞれの選択肢を見ていきます。
各選択肢の分析
a 輸出の増加によって日本の経常収支の黒字が拡大すると、為替レートには円高ドル安の圧力が働く。
輸出が増加すると、日本に対する需要が増え、その結果、日本円の需要が高まります。これにより、円高ドル安の圧力が働くという考え方は正しいです。
b 輸出の増加によって日本の経常収支の黒字が拡大すると、為替レートには円安ドル高の圧力が働く。
輸出が増えると円の需要が増加し、円高の圧力がかかるため、この記述は誤りです。
c 米国の金融資産の収益率が高くなることで日米の金融資産の収益率の格差が拡大すると、日本の金融収支は赤字になり、為替レートには円高ドル安の圧力が働く。
米国の金融資産の収益率が高くなると、投資家は米国資産を買うためにドルを購入します。ドルへの需要が高まり、通常は円安ドル高の圧力がかかるため、この記述は誤りです。
d 米国の金融資産の収益率が高くなることで日米の金融資産の収益率の格差が拡大すると、日本の金融収支は黒字になり、為替レートには円安ドル高の圧力が働く。
米国の金融資産の収益率が高まると、米国への投資が増え、ドルの需要が高まります。この結果、円安ドル高の圧力がかかります。日本は長期的に経常収支が黒字であるため、海外に対して多くの金融資産を保有しています。特に、米国などの金融資産を保有することで、受け取る利子や配当などの形で利益を得ており、その結果、日本の金融収支は黒字となる傾向があります。この記述は正しいです。
適切な組み合わせ
最も適切な選択肢は「 aとd」です。
問題に戻る
第10問
下図によって、完全資本移動かつ小国のマンデル=フレミング・モデルを考え
る。政府支出拡大の効果に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答
群から選べ。

a この国が為替レートを維持しようとするならば、政府支出の拡大は、為替レー
ト維持のための自国通貨の売り介入に伴う貨幣供給の増加と相まって、自国の
GDPを増加させることができる。
b この国が為替レートを維持しようとするならば、政府支出を拡大させても、為
替レート維持のための自国通貨の買い介入に伴う貨幣供給の減少と相まって、自
国のGDPを減少させてしまう。
c この国が為替レートの変動を市場に任せるとき、政府支出を拡大させても、そ
の効果は資本流入の増加による自国通貨高によって完全なクラウディング・アウ
トが生じ、自国のGDPは増加しない。
d この国が為替レートの変動を市場に任せるとき、政府支出の拡大は、為替レー
トを減価させ、自国のGDPを増加させる。
- aとd
- bとd
- bとc
- aとc
正解!
不正解...
正解はaとcです。
a:固定相場制+政府支出拡大 → GDP増加
政府支出の拡大 → IS曲線右シフト → BPとのズレ(資本流入) → 通貨高圧力
中央銀行が通貨高を防ぐために 自国通貨を売って外貨を買う → マネーサプライ増加
LM曲線も右シフトし、GDPは増加
✅ 正しい
b:固定相場制+政府支出拡大 → GDP減少
aと逆の内容。通貨買い介入は起こらない。固定相場制では「売り介入」が通例。
❌ 誤り
c:変動相場制+政府支出拡大 → GDP増加しない
政府支出の拡大 → IS曲線右シフト → 金利上昇 → 資本流入 → 通貨高 → 輸出減・輸入増
通貨高による純輸出減少がISを押し戻す(クラウディングアウト)
結果、GDPは増えない
✅ 正しい
d:変動相場制+政府支出拡大 → 通貨安→GDP増加
政府支出拡大はむしろ金利を上げる→資本流入→通貨高になるため、通貨安は起きにくい。
❌ 誤り
問題に戻る


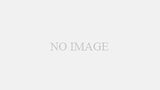
貨幣需要に関する記述の正誤を検討すると、以下のようになります。
a:誤。利子率が上昇すると、取引動機による貨幣需要は通常減少します。利子率が高いと、貨幣を持つことの機会費用が増えるため、貨幣を保有するインセンティブが減ります。
b:誤。物価上昇は現金の実質価値を減少させるため、資産選択の動機による貨幣需要は通常増加します。
c:正。利子率が上昇すると、安全性の高い現金の魅力が相対的に減少し、資産選択の動機による貨幣需要は減少します。
d:正。将来の不確実性が高いと、利子率が上昇しても予備的な動機による貨幣需要は増加する傾向があります。人々は不確実な状況に備えて、現金を保持することを選ぶからです。
したがって、正しい組み合わせは次のようになります:
a:誤 b:誤 c:正 d:誤